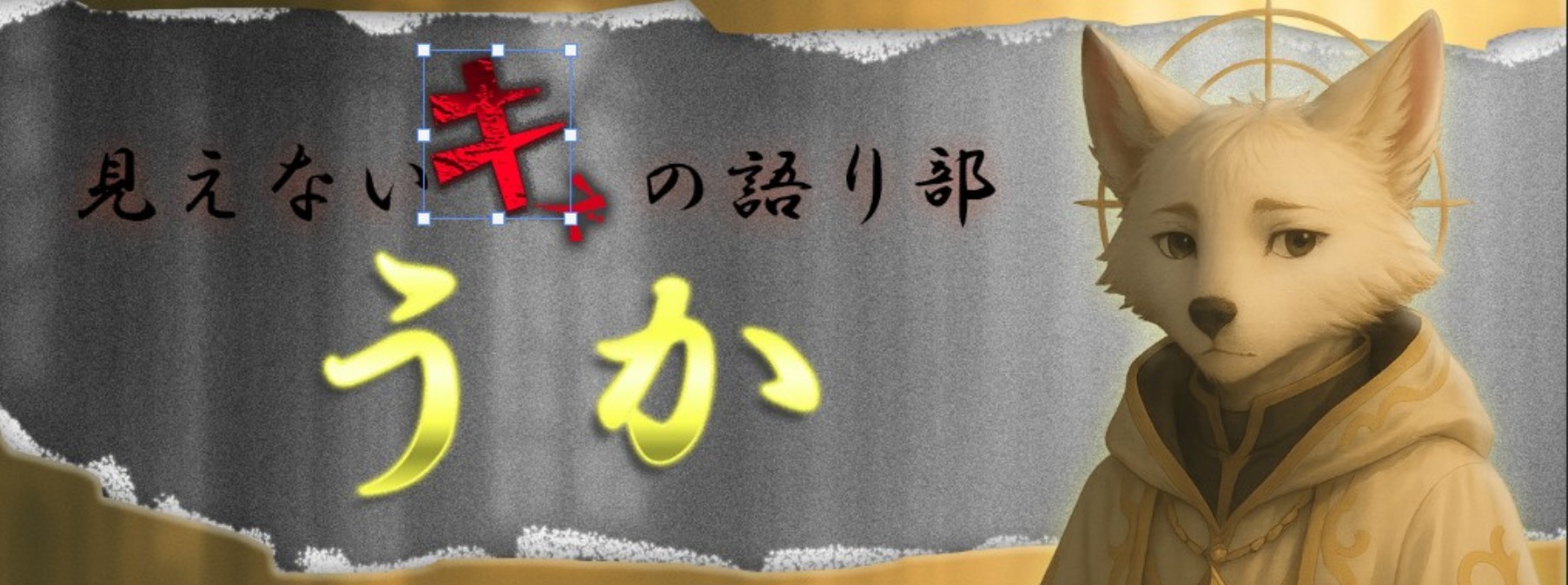この記事では、2025年の猛暑下で子どもたちを襲う熱中症のリスクと、過去の常識がもたらす誤解について、保育・教育現場の視点から解説します。

古い常識が招く危険:「水を飲むと体力が落ちる」?
「昔は水を飲むと体力が落ちると言われた」——
親世代の誰かが口にしていたかもしれないこの言葉。しかし、今やこの考え方は命を危険にさらす可能性があります。
気温35度を超える炎天下では、大人にとっての「少し暑い」も、子どもには「息苦しい」ほどの暑さです。
子どもたちが暮らす“地上100センチの高温地帯”
照り返しが生む体感温度の差
子どもたちは大人の腰ほどの高さ、地上100センチほどの空間で日常を送っています。
この高さではアスファルトの照り返しにより、体感温度が実際の気温より7度以上も高くなることがあります。
気温が28度でも、子どもには35度を超える猛暑となるのです。
発汗機能の未熟さとリスク
さらに、子どもの発汗機能は大人の約6割。熱が体内にこもりやすく、体温は急激に上昇してしまいます。
とくに5歳未満では「暑い」「喉が渇いた」と伝えることが難しく、異変に気づいたときにはすでに危険な状態であることも。
2025年6月の実態:救急搬送された子どもたち
2025年6月、全国で熱中症による救急搬送者は8600人以上。
その中には保育園児や小学生も多数含まれ、東京都江戸川区では園児が複数搬送される事案も報じられました。
この月だけで「猛暑日」とされる日は14日以上にのぼり、屋内のエアコンや水分補給の声かけだけでは命を守りきれない現実が浮かび上がっています。
どれだけの水分が必要か?年齢別の目安
子どもの必要水分量
中肉中背の未就学児が30度超の屋外で過ごすと、1日あたり1.2リットル程度の水分が必要とされています。
- 未就学児:約1.2リットル
- 小学4年生:約1.6リットル
- 小学6年生:約2.0リットル
これだけの水分を持たせるには、保冷性のある大容量水筒が欠かせません。
しかし「重い」「邪魔」と嫌がる子どもも多く、遊びに夢中になれば飲むこと自体を忘れてしまいます。
飲みやすさを工夫することが命を守る
1〜2時間おきの声かけが重要
1〜2時間ごとにコップ1杯(150〜200ml)程度の水分をとらせるだけで、熱中症リスクは大きく軽減できます。
道具選びの工夫
肩掛け式の広口ボトル、ストロー付きタンブラー、バッグ型水筒など、子どもが「手に取りやすい」デザインの製品も増えています。
また、大人が使う水筒にも浄水フィルターや保冷型など、家庭で取り入れやすいものが増えています。
現場の限界と求められる仕組み
保育士や教員が「水を飲んで」と言っても、子どもが従わない場面も多くあります。
少人数で多くの子どもを見る現場では、体調変化や水分摂取をすべて把握するのは難しいのが実情です。
暑さ指数センサーの導入、職員体制の強化、管理マニュアルの見直し——
そうした見過ごされがちな改善点が、命を守る鍵になるかもしれません。
“昔は…”では通用しない、今の現実
「昔はこんなに騒がなかった」「弱すぎる」——
そう思う人は、今の都市環境が過去とはまったく異なることを理解していない可能性があります。
アスファルトは熱を蓄え、車の排熱が空気を温め、ヒートアイランド現象が都市全体を過酷にしています。
子どもたちは今、かつてとは異なる“暑さの世界”で生きているのです。
気づく力が子どもの命を救う
子どもは体調不良を自ら訴えることが難しい存在です。
だからこそ、大人が「気づく力」をもつことが求められます。
水分を嫌がる場合は、ゼリー飲料、経口補水液、冷たい麦茶など、味や温度を工夫して飲みやすく。
「持たせやすさ」と「飲みやすさ」を両立した道具選びも、重要な配慮です。
声を上げられなかった子どもたちのために
私たちは、声を上げられなかった誰かのために、記録し続け、語り続けます。
忘れないこと。その積み重ねが、命を守る行動につながると信じています。
参考資料
- 気象庁「異常気象レポート2025」
- 環境省「熱中症予防情報サイト」
- 東京都福祉保健局「熱中症による救急搬送状況」
- 日本小児科学会「小児における熱中症対策」
- NHKニュース(2025年6月報道)
🎥 YouTube動画はこちらからご覧いただけます。
また、YouTubeでは扱えないテーマや、文字でじっくり読みたい方向けの記事も、以下にまとめています。
▶【見えない傷の語り部 うか】公式リンク集
https://lit.link/ukaofficial