この事件は、あなたの子どもが通う教室で起きていたかもしれません。福岡県で複数の教員がわいせつ行為を理由に処分されながら、その多くが非公表とされていた事実をご存じでしょうか。
なぜ公表されなかったのか。誰の意思で、誰のために、その決定がなされたのか——
今回は、「記録されなかった罪」について考えます。
福岡県で相次いだ非公表処分の実態
2021年以降、福岡県内で教員による不適切行為に対する懲戒処分が相次ぎました。
しかし、多くの事案が「非公表」とされ、教員名や学校名、さらには処分理由までもが伏せられていたのです。
その結果、保護者や地域住民は何が起きたのかを知らされず、日常を過ごすことになりました。
📍事例①:2021年・中学校での不適切接触
県内中学校の教員が生徒に不適切な接触行為を行い、懲戒免職に。
県教育委員会は「被害者保護」を理由に、加害者の氏名や学校名を一切公表しませんでした。
同じ学校の保護者にも事件の存在が伝えられず、学校という共同体に亀裂を生んだ可能性があります。
📍事例②:2022年・県立高校教員の身体接触
県立高校の男性教員が停職6ヶ月の処分を受けたものの、詳細は「個人情報」として非公開。
報道では「不適切な身体接触」があったとの証言もありましたが、公式な確認はされていません。
教員はその後退職し、再就職先での情報共有も行われていません。
📍事例③:2023年・再就職先で問題が判明
非公表で処分された元教員が県外の教育関連施設に再就職していたことが発覚。
経歴照会で問題が表面化せず、保護者団体の抗議によって再調査が行われました。
この事案は、非公表処分が再発リスクを生む構造的な問題を示しています。
非公表の“理由”に潜む構造
福岡県教育委員会は「本人の名誉を守るため」として非公表を正当化しています。
しかし、その“名誉”とは誰のものでしょうか。
被害を受けた子どもやその家族の尊厳は、どこにあるのでしょうか。
「被害者を守る」という建前が、実際には加害者を守るための口実になっていないか——
私たち一人ひとりが、その視点を持つことが求められています。
学校名すら明かされないという現実
ある日突然、その教員はいなくなり、「体調不良」とだけ説明される。
子どもたちや保護者は「何があったのか」を知らされないまま、日常を続けます。
それで本当に、再発防止につながるのでしょうか。
事実を知らなければ、教訓も学べない。不信感と不安だけが残ります。
市民に問われる“知る権利”
教職追放制度や懲戒記録の照会制度はありますが、申告ベースでの運用には限界があります。
非公表とされた処分は情報開示の対象外であり、別自治体や私立校、塾への再就職を完全には防げません。
保護者ができることも限られています。だからこそ、知る権利と公的記録のあり方そのものが問われているのです。
声を上げられなかった子どもたちのために
記録されなかった罪、知らされなかった不安。
声を上げられなかった子どもたちの代わりに、私たちは記録し続けます。
忘れないこと、語り続けること——その積み重ねが、誰かを守る力になると信じて。
あなたは、“知らされなかった不安”を抱いたことがありますか?
参考資料
- 福岡県教育委員会 公表資料(2021〜2023年)
- 西日本新聞「県教委が教員処分を非公表」
- NHK福岡「処分理由非公開に保護者団体が抗議」
- 教育と人権ネット「再就職後の情報開示に関する検討会報告」
この記事の内容は、YouTubeチャンネル「見えない傷の語り部 うか」でも配信中です。
🎥 YouTube動画はこちらからご覧いただけます。
また、YouTubeでは扱えないテーマや、文字でじっくり読みたい方向けの記事も、以下にまとめています。
▶【見えない傷の語り部 うか】公式リンク集
https://lit.link/ukaofficial
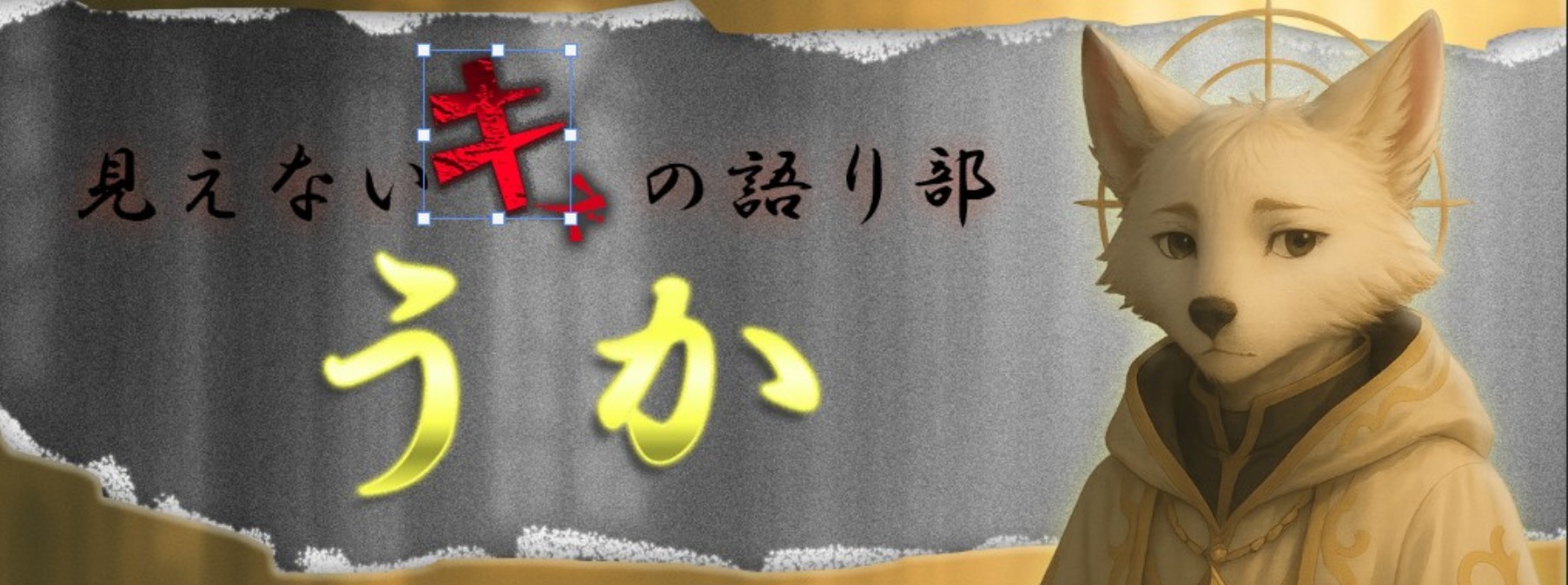



コメント