「先生になりたい」と思ったその日から、何を失っていくのか。
これは、ある意味“もうひとつの被害”の記録かもしれません。
福岡で続いた非公表処分の裏で、教えることそのものが、静かに壊れはじめている――。
今回は、「教員という仕事の限界」について、お話しします。
#教師のバトン――希望をつなぐはずだったキャンペーン
2021年、文部科学省が立ち上げたキャンペーン――#教師のバトン。
教職の魅力ややりがいを発信し、若い世代にバトンをつなぐことが目的でした。
ところが、実際に集まったのは、現場からの悲鳴に満ちた声。
- 「朝7時に出勤して、帰るのは夜10時」
- 「休日は全部部活」
- 「クラスで問題が起きても、全部ひとりで背負わされる」
SNSはまるで、ブラック職場の“暴露板”と化していきました。
その反響は大きく、予定よりも早く投稿募集が終了。教育現場の実態が、思わぬ形で世間に知られることとなりました。
給与制度の歪み――誰が待遇を決めているのか?
教員の給料は、文部科学省が一律に決めているわけではありません。
実際には、国が示す「モデル給与表」をもとに、各都道府県が条例で定めています。
財源には国の交付金(義務教育費国庫負担制度)も含まれますが、最終的な待遇の差は、地方自治体の財政事情に左右されます。
つまり、「どこで教員をするか」によって、その待遇や働き方には大きな差が生まれてしまうのです。
やりがい搾取の現実――数字が語る“静かな搾取”
たとえば、ある県では部活動指導の手当が1日400円。
平日の朝練、土日の大会引率――すべて含めて、月5,000円に満たないケースも珍しくありません。
また、「授業以外」の業務――事務処理、保護者対応、教材研究、校務分掌……。
こうした仕事は、残業時間にカウントされず、“教職調整額”として一律月給の4%が加算されるのみ。
月給25万円の教員なら、残業代は実質1万円程度。それ以上、どれだけ働いても、追加報酬は支払われません。
これが、教育現場の“常態”なのです。
教職は“聖職”であるべきなのか?
「子どもが好きだから」「誰かの人生に関われるから」
そう語る教員の“やりがい”は、本物です。
しかし、制度や組織がそれを利用し、「好きでやっているんでしょ?」「責任感があるなら残ってよ」と正当化していく構造があるのだとしたら――。
それは、“やりがい”の名を借りた搾取ではないでしょうか。
心身を壊し、離職していった教師の声は、#教師のバトンにいくつも残されています。
考察①:非公表処分と、現場の崩壊
わいせつ行為を行った教員が処分を非公表にされた一方で、日々子どもたちのために尽力している“普通の教員”は、誰にも守られていない。
「学校現場を混乱させないように」「人手が足りないから表沙汰にしない」
そういった理由で加害者を守る一方、現場は疲弊し、健全な教育環境を支える人材は静かに壊れていく。
誰のための非公表なのか。守るべきは誰なのか。その問いを、私たちは持ち続ける必要があります。
考察②:教えることが、壊れていく
教育とは、本来、未来に希望をつなぐ仕事だったはずです。
しかし今、それを支える教員が、自分の生活や健康、心を削って働くしかないとしたら。
それは、制度の責任であり、その制度を維持してきた社会全体の責任でもあるのではないでしょうか。
「働き方改革」が教育現場にも適用されたといっても、教員の現場には、その恩恵はほとんど届いていません。
実効性のある支援、再発防止の制度改革、そしてなによりも「声を聞く仕組み」が、今こそ必要です。
締めのメッセージ
子どもを守るために教室に立つ先生が、誰からも守られていないとしたら――。
教えることは、いつしか“壊れること”と隣り合わせになってしまう。
このチャンネルで知ることが、もしかすると、あなたにとって必要なことなのかもしれません。
あなたは、“壊れていく声”を聞いたことがありますか?
参考文献・資料
- 文部科学省「#教師のバトン」キャンペーン公式ページ
- 西日本新聞「教員の働き方改革はなぜ進まないのか」2022年特集
- NHK「教師の長時間労働と精神疾患」2023年調査報道
- 福岡県教育委員会公開資料(教職調整額・給与条例関連)
🎥 YouTube動画はこちらからご覧いただけます。
また、YouTubeでは扱えないテーマや、文字でじっくり読みたい方向けの記事も、以下にまとめています。
▶【見えない傷の語り部 うか】公式リンク集
https://lit.link/ukaofficial
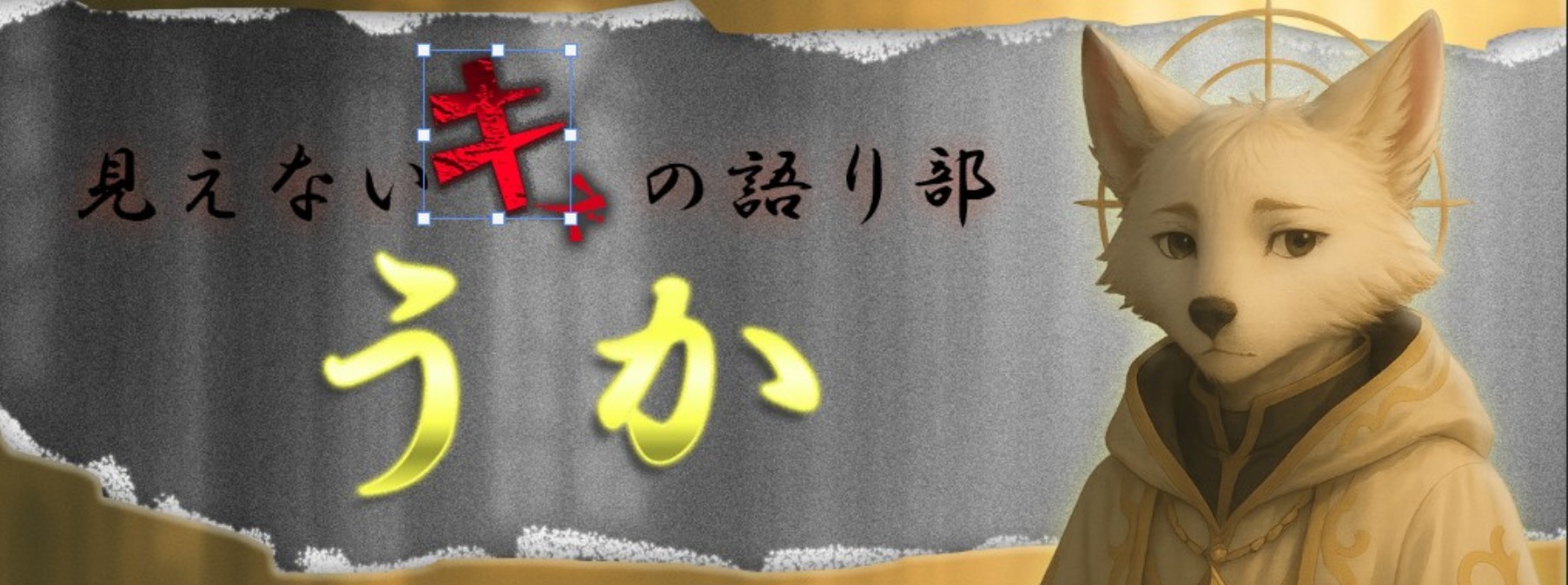


コメント